こんにちは!はねうさぎ(@haneusagi_com)です。
12月24日はクリスマスイブです。
つい先日、ツイッター(X)で「12月24日を祝うのは日本くらいじゃない?」どいうコメントを見かけました。
実際、世界各国ではどうなんでしょうか。
例えば、私が以前住んでいたアメリカでは24日は特別な日ではなく、25日に家族や友達が集まり、ごちそうを食べる習慣があり、12月25日を祝う習慣がありました。
イタリアも25日がメインにお祝いする日なんだとか。
ではドイツはどうでしょうか。
クリスマスツリーは24日に飾るのがドイツ流
ドイツでは、伝統的にクリスマスツリーを12月24日のクリスマスイブに飾りつけします。
このウェブサイト「Christmas around the world」によりますと、世界で初めてクリスマスツリーを家に飾ったのはドイツ人だと言われているとのことです。
いろんな国に友人がいる私は、SNSでは「クリスマスツリー飾った!」というレポートと共に居間に飾り付けられたクリスマスツリーの写真を拝見することもしばしば。
これが、大体12月の始めごろが多いです。
イギリスやアメリカの英語圏はそんな感じですし、北欧、南ヨーロッパもそんな感じ。
でもドイツは12月24日まで飾りません。
クリスマスツリーを購入しておくのですが、お部屋に持ってきて飾るのは12月24日。
他の国もそうですが、ドイツではクリスマスツリーを1月初めまで飾っておきます。
大抵の家庭が1月6日の「Heilige Drei Könige(ハイリゲ・ドライ・ケーニゲ)」と言われる東方三博士の日くらいまで飾っておきます。
なぜドイツではクリスマスツリーを12月24日に飾るのか?という質問に対しては「伝統だから」と言う回答が多いのですが、中には「葉が落ちて掃除が大変だから」という人もいます。
そう。奇麗好きのドイツ人。
確かに、アメリカに住んでいた時、毎週末にクリスマスツリーの下を掃除機かけていたなあと、思い出しました。(ちなみにドイツでは日曜日に掃除機をかけるのは非常識と思われています)
また、ドイツでは「アドベント」と呼ばれるクリスマス前の4週間を祝う習慣もあり、ドイツ人は首を長―くしてクリスマスまでの日程を楽しみます。
>>あわせて読む
【ドイツではクリスマスイブを盛大に祝う】ホリデーシーズンを満喫
「クリスマスイブを祝うのって日本だけじゃない?」
いやいや、そんなことはありません!
ドイツでは、もちろんキリスト誕生の日は12月25日なのですが、24日にクリスマスツリーを飾り、そのまま家族でクリスマスを祝う重要な日です。
ドイツもクリスマスイブが最重要日なのです!
私達は、家族皆で教会へ行き、その後「クリストキント」と呼ばれる、日本やほかの国だと「サンタクロースがプレゼントを持ってくる」のと同様に、クリストキンドがクリスマスツリーの下にプレゼントを持ってきます。
クリストキントがプレゼントを持ってくると、ベルが鳴り、皆で居間へ移動してプレゼントを開けます。(大抵はお母さんが準備している)
そして、その後夕食となります。
【訂正】この記事を書いた後に、この順番が間違いだったことに気づきました・・・。
ディナーの後にクリストキントが来て、皆でプレゼントを開けました。
ご家庭や家族構成によって、教会~プレゼント~クリスマスディナーの順番は異なるかと思います。
教会(17:00からのミサを狙って、その時間にミサが行われている近くの教会へ行く)~クリスマスプレゼント~夕食でした。
私にもクリストキントが来ました!^^
はねうさ夫曰く、彼がまだ小さかった頃は、12月24日、25日、26日と3日間の間毎日教会へ行ったそうです。
今でも毎日行く人もいるようですが、私たちの家族は簡略化し、24日だけ教会へ行くようになったということです。
ちなみに、教会では、子供たちによって「Krippenspiel(クリッペンシュピール)」とか「Kinderspiel(キンダーシュピール)」と呼ばれるイエス・キリストの誕生劇が上演されます。
これを楽しみにしている方々もいるかと思うのですが、うちの家族は「つまらない!時間の無駄!」「ぜんぜんイケてない!」と大不評・・・苦笑
いろんなドイツ人がいますね!(笑)
クリスマスイブ12月24日はドイツでは祝日なの?
12月24日のクリスマスイブは、ドイツでは正式な祝日ではありませんが、日本の大晦日をイメージしていただけると分かるように、ほとんどの会社がお休みとなります。
正式には、12月25日と26日が祝日ですが、12月24日は、お店は14:00で閉まるところが多いです。
会社の場合は、その年のカレンダーにもよりますが、24日は会社が従業員にお休みを与える場合がほとんどです。
日本の大晦日の習慣にすごく似ていると思います。
ドイツ人はクリスマスに何を食べるの?!特別な食事はある?
夕食は、ドイツの伝統的なクリスマス料理をいただく家庭が多いようですが、我が家(というか、はねうさ夫の実家)は、少しファンキーなドイツ人なので?!毎年メニューが違います。
私がドイツに引っ越してきた初年度は、マグロやサーモンなどのお魚でした。
2年目の昨年は、鯉のフィレ。これまたお魚で、私たちの住んでいる地域では、鯉を食べる習慣があります。
今年は何かというと「フォンデュ」です。
※ちなみに、夫に確認したら「チーズフォンデュではない」とのこと・・。何なんだろう!
【追記】
チーズフォンデュではなく、オイルフォンデュと呼ばれるものでした!
油脂を溶かして液体状にした揚げ鍋の中に、スティックに刺したお肉を入れて素揚げにした後、ソースにつけていただくものでした。
豚肉、子牛、牛肉を用意してくれていて、初めていただきましたがとても美味しかったです。
ソースは全て義理母手作りで、カレーソース、レモンタルタルソース、パプリカソース、アボカドソース、ロックフェラー(ブルーチーズ)ソースの5種類とこれまた手作りのハーブバターと、6種類のオプションでした!
フランス語ですが、Wikipediaがありましたのでリンクします。写真でイメージ付くでしょうか?!
クリスマスが近くなると、義理母から「クリスマスプレゼントと誕生日プレゼントは何が欲しいの?(私の誕生日が1月な為)」「クリスマスはフォンデュかサーモンどっちがいい?」などと質問攻めにされます。
他のご家庭は割とドイツの伝統的な料理が多いようですが、家庭によって食べるものは違うようですが、やはり肉とジャガイモというのが多いらしいです。
お肉は、牛肉だったり、鴨肉だったり、七面鳥だったり、ウサギ肉だったり様々。
はねうさ夫のおばあさんが亡くなるまでは、ソーセージにポテトサラダを毎年クリスマスに食べていたようで、意外と質素な内容ですね。
料理大好きな義理母は、志向を凝らしたお料理でお祝いしたい気持ちがあるようで、我が家では「典型的なドイツ料理」をイメージするものは食卓にあまり上がりません(笑)
【追記】今年12月25日のクリスマス当日の昼食は、この地域の伝統的な食事でした。これはこれで私は好きなので美味しかったです。
そして、ビールにワインを飲みまくる・・・というのは、日本と一緒でしょうか。
日本の大晦日やお正月をイメージしていただけると、想像がつきやすいかもしれません。
ドイツではなぜ12月24日のクリスマスイブを盛大に祝うのか
色々なサイトを調べたり、ドイツ人にこの「ドイツではなぜ12月24日を盛大に祝うのか?」という質問をしても、誰も明確な答えをくれなかったりするので、理由ははっきりわかりません。
ドイツ人はせっかちだから・・・なんていう人もw
ただ、私が考えるに、ドイツ人は、前夜を祝うのが好きなのかなあと・・・単純に。
例えば、ドイツ人の誕生日の祝い方というのがあって、その人の誕生日の前日の夜に仲間同士で集まり、夜中に日付が変わって誕生日になる時に「カンパーーイ!」「お誕生日おめでとう!」というパーティーをやる習慣があるのです。
ですので、前夜祭とか、日付が変わる時に祝うとか、そういった習慣がドイツにはあるような気がします。
個人的には、おそらく日本人がクリスマスイブを祝う習慣は、ドイツから来たのではないかと推測しています。
戦前戦後の日本にとって、ドイツはヨーロッパの大国で見習うべきものが沢山あったし、ドイツから日本へ導入されたシステム(例えば法律的な部分や健康保険、政治的な制度など)も多くあります。
なので、日本にとってドイツは「参考にすべき友」であり、追いつき追い越せという存在だったことが言えると思います。
バブル景気のころは、「12月24日に赤プリを1年前から予約し、プレゼントは高級ブランド品が当然」だったわけですが、この辺も西洋の文化を生活に取り入れることがカッコイイ時代でしたので、12月25日よりは24日の前夜祭的な方が経済効果が高かったのかなあ・・・と、考えてみたりしています。(時代を感じますね!)
今となっては、アメリカの影響を多く受けている日本ですので、近年の日本の家庭や若者の間では、12月25日にクリスマスを祝う人もいますね。
さあ、そろそろドイツ時間でランチタイムです。
出かける準備をしないといけないので、そろそろ終わりにしますが、皆様もぜひ素敵なクリスマスをお過ごしくださいね!
Wir wünschen euch Frohe Weihnacht (Merry Christmas) !!
Ciao~!
【追記】
この記事を書いた後に知ったのですが、「公式の」「本来の」教会で行われるミサは22:00からだそうです。
ミサが終わるころになると、ちょうど深夜前後になり、25日のクリスマス当日を迎えることになるため、本来は24日の夜遅くのミサに行くのが正式とのことです。
ミサは、色々な時間に行われますが、私達はここ数年、17:00開始のミサに行って、家に戻ってから食事をするという流れになっています。
けれども、義理両親は夕食と一緒にワインを飲みたいので、おいしい食事やワインを楽しんだ後に教会のミサに参列するのは嫌なんだそうです。
まあ・・・そうですよね。車で行く必要があるので、運転を考えると飲めないし、教会は寒いしで良いことありません(苦笑)
しかし、この事実を考えると、やはりドイツには日付をまたがって行事をお祝いする習慣があるのだと改めて思いました。
実は、私の出身地域も「二年参り」といって、行く年と来る年を同時に祝うために0:00前に神社へ行き、神社で新年に日付が変わるのをお祝いする風習があります。
神社へお参りに来ている近所地域の方々を少しお話をしたりします。
神社ではお酒が無料でふるまわれ、屋台でおでん(温かいこんにゃく)や干物、子供向けのチョコバナナ等を買うことができます。
深夜寒い中で飲むこの日本酒がまた、おいしいんだなあ~~~(笑)
>>あわせて読む
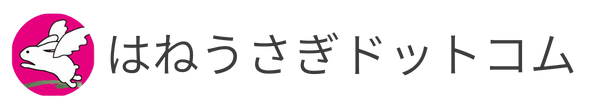





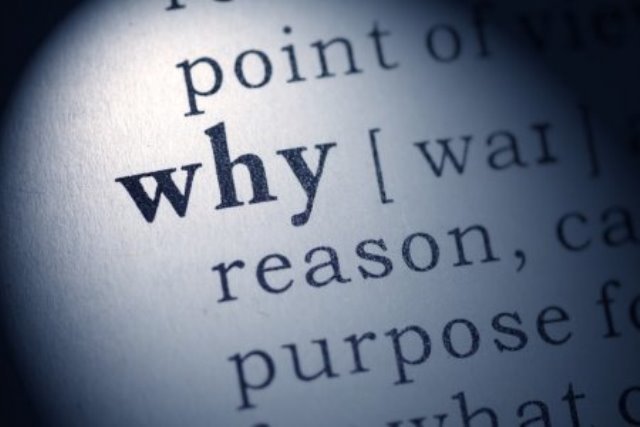
コメント