こんにちは!はねうさぎ(@haneusagi_com)です。
Zeckenbiss ドイツドイツに住んで8年になりますが、先日ついに「マダニ(Zecke)」に刺されてしまいました。
日本にいる看護師の友人から、「ドイツではマダニに注意して、予防接種(FSMEワクチン)も受けておくといい」とアドバイスを受けていたにもかかわらず、「森なんて行かないし、自分は大丈夫」と思っていた私。
けれど、まさか自分が刺されるとは…。
今回は、気づかぬうちに刺されていたマダニの発見から、ドイツの病院での診察、そして学んだ教訓まで、実体験をもとに詳しくお話しします。
※虫や傷の写真は掲載していませんので、安心して読んでいただけます。
森でのキノコ狩りがきっかけに(振り返ってみると)

刺されたのは、おそらく9月終わりの週末。
義理の家族と一緒に、湿った苔が生える森へキノコ狩りに出かけました。
朝の森は霧が立ちこめ、木々の間に光が差し込む幻想的な雰囲気。
ルンルンの中、2時間ほど歩きながらバスケットいっぱいのキノコを採りました。
ただ、地面は前日の雨でしっとりと湿っており、靴も靴下もびしょ濡れ。
義理両親の家に戻ったとき、着替えを持っていなかったため、靴下だけ替えてランチへ。
濡れた靴はドライヤーで半分ほど乾かし、午後はそのまま地元のお祭りへ行き、ワインを飲んで帰宅しました。
 はねうさぎ
はねうさぎマダニは湿った環境が好きなようです。
今振り返れば、このときシャワーを浴びずに過ごしたことが最大の落とし穴だったと思います。
森歩きのあとは、必ず全身チェックと入浴をしましょう!
ズボンの裾などにくっついて刺す場所を探して移動するらしいのです!(怖)
これは今回の経験から強く伝えたいことです。
異変に気づいたのは森へ行ってから4日後

森へ行った日から4日後、所用でミュンヘンに行き、ホテルにチェックインした時のこと。
部屋に入り、スリッパに履き替え、部屋で少しくつろいでいた時のこと。
靴下の上あたりの、ふくらはぎ内側にチクッとした感覚がありました。
見ると、小さな赤茶色い「かさぶた」のようなものが。
「虫に刺された跡かな?」と思い込み、触っても取れなかったため、そのまま放置してしまいました。
友人とオクトーバーフェストへ行き、夕食を食べて気分良くその日は就寝し、翌日友人とカフェに行ってまたまたルンルンでオーストリアへ移動しました(この時は気楽過ぎた)。
オーストリアのチロル地方に移動して「かさぶた」を確認しましたが取れず。
少しだけ「かさぶた」周辺が赤くなっていました。
日曜日になり、ふと太ももを見ると、その「かさぶた」の周囲が赤く腫れ、痛みもありました。
よく見ると、かさぶた自体が灰色っぽく変色して丸くふくれている…。
「これはさすがに何かおかしい」と思い、ひねって取ろうとした瞬間、ポロッと取れて床に落ちました。
ゴミ箱に入れようと、拾い上げようとしたその瞬間に、「かさぶた」が動いたのです( ゚Д゚)
 はねうさぎ
はねうさぎマダニは血を吸い始めた時は赤茶色でだんだんと膨らんで行き、グレーっぽくなっていくらしい(ウゲー!すでにホラー!)
「かさぶた」だと思っていたものはマダニだった

一瞬、何が起きたのか理解できませんでした。
床に落ちた小さな塊がモゾモゾとゆっくり動いていて、よく見るとクモのような脚が。
思わず息をのみました。「これ…虫だったの!?(((;゚Д゚))」
慌ててスマホで虫と赤くなった患部を撮影し、ChatGPTに経緯を説明してこの虫が何なのか教えてもらう事にしました。
 はねうさぎ
はねうさぎ今までの人生で一度も見た事のない虫だったからです!
そして、「マダニ(Zecke)の可能性が高い」という返答が返ってきました。
ドイツ語で「Zecke」と呼ばれるこの虫は、人や動物の血を吸い、感染症を媒介する危険な虫で、しかも、吸血中は痛みを感じにくく、数日間皮膚にくっついたままになるのだと知りました。
マダニの可能性を考慮して、すぐにシャワーで刺された患部をよく洗いました。
マキロンのような消毒液が自宅にあれば、まずは消毒し、その後クリニックを受信することをお勧めします。
また、マダニは一度狙った場所を刺すと、シャワーやお風呂でも流れないため(実際に何日もシャワーしていましたが取れずにくっついていました)、皮膚に刺し着いた状態でクリニックを受診して、医師からとってもらう方法もあります。
無理やり強く引き離すのはやめましょう!
オーストリアからドイツへ戻る道中での応急処置

マダニは様々な病原菌を媒介するらしく、刺されたことに気づいたら24時間以内に医師に診てもらう事をGPTから推奨されました。
ところが、日曜日で医者も薬局(Apotheke)も閉まっていたため、どうすることもできず…..。
 はねうさぎ
はねうさぎこういう時に本当に困るドイツ(ヨーロッパ)生活….
まず、オーストリアに滞在していたためドイツの保険証が使えないので、ドイツ側へ戻る途中で緊急で診てもらえそうなクリニックや日曜日も開いている薬局へ片っ端から電話(夫からしてもらいました)。
しかし、ここはドイツの洗礼とも言える「緊急の電話番号にかけても誰も電話に出ない」とか「日曜日用の電話番号にかかってるけど、私は自宅から電話番のためだけに働いている薬剤師です」みたいな方から塩対応されたりしました(((;゚Д゚))
ダメもとで医師の友人に写真を送り、電話して相談したところ、「間違いなくマダニだから、抗生物質入りのクリームを塗るといい」とアドバイスを受けました。
そして、ミュンヘンで日曜日も開いている薬局を見つけて電話したのですが、医師の処方箋無しでは抗生物質入りのクリームは販売することができないと言われてしまいました。
 はねうさぎ
はねうさぎ「ドイツあるある」すぎる….( ゚Д゚)
友人の好意に甘え、帰路の途中に友人宅へ立ち寄り、薬を分けてもらって帰宅後すぐに塗布しました。
ちなみにライム病、マダニ、などなどのキーワードで色々と検索すると、沢山の情報が出てきて怖かったです。。。
ドイツのクリニックでの診察

翌日の月曜日、近所のクリニックを受診しました。
 はねうさぎ
はねうさぎドイツは三連休後の月曜日だったので、クリニックの外にまで長蛇の列でした(泣)
まず、受付で、マダニがまだ皮膚に着いた状態なのかすでにとってしまった後なのかを確認されました。
私は取ってしまった後だったので、その旨を説明。混んでいたのでその日の午後にもう一度来るように言われました。
医師に状況を説明し、刺された部位を見せたところ、注射針のようなもので患部を刺して診てくれ「口(頭部)は残っていないから問題ないでしょう」とのこと。
ヨード入りの軟膏を塗ってもらい、あとは経過観察のみで、「もし刺された場所を中心に赤いリング状の症状が現れたら、すぐにまた受診してください。その場合はライム病の症状の可能性があります」と言われました。
抗生物質の内服や血液検査などはなく、診察はわずか5分ほどで終了しました。
「え、これだけ…?(それもヨード入りクリームって昭和時代の赤チンキでは..?)」と少し不安に思いましたが、ドイツではマダニ咬傷の多くが消毒と経過観察扱いで、症状が出た場合のみ追加検査になるようです。
予防接種を勧められていたけれど…

実は、ドイツ移住前に日本の友人(看護師)から「ドイツへ移住するならマダニには注意してね」と念押しされていました。
特に南ドイツ(バイエルン州やバーデン=ヴュルテンベルク州)では、FSME(Frühsommer-Meningoenzephalitis/ダニ脳炎)ワクチンの接種が推奨されていますし、オーストリアでもほとんどの人がワクチンを接種しているようです。
「街生活が好きな自分は、森になんて行かないから大丈夫」と軽く考えていた私。
けれど、今回のようにちょっとしたキノコ狩りやピクニックでも刺されるリスクがあることを痛感しました。
「自分には関係ない」と思っている私のような人ほど、注意が必要なのかもしれません(苦笑)
ドイツでマダニに刺されたときの注意点

実際に刺されてしまった経験から、特に気をつけたいポイントをまとめます。
- 無理に引き抜かないこと!
→ 頭が皮膚に残ると感染のリスクが上がります。ピンセットや専用ツールで慎重に。 - オイルやアルコールをかけない
→ マダニが苦しんで唾液を多く出し、感染リスクが高まる可能性があります。 - できるだけ早く医師へ
→ Hausarzt(かかりつけ医)や皮膚科、休日ならNotaufnahme(救急外来)へ。 - マダニを保管して医者に見せるのも有効
→ 感染性の有無を調べられることがあります。
 はねうさぎ
はねうさぎApothekeの入り口などに日曜・祝日の緊急連絡先が書いてある場合もあります。
刺されたとき・発見後にあると便利な道具・薬

ここでは、マダニ刺傷時やその後に備えておくと安心な ツール・消毒薬・市販薬 を紹介します。
ただし、薬選びは国・地域の規制によりますので、「あくまで参考」情報としてお読みください。
マダニの除去ツール(マダニを安全に取り除くために)
なんと、マダニを正しく除去するための道具が販売されています。
ドイツの薬局(Apotheke)やオンラインで買えるものをいくつか紹介します。
いずれも「頭を残さず、つぶさず、ゆっくり取り出す」ことを目指す設計のもので、私がくるっとひねって取ったのは偶然ではありますが、不幸中の幸いにもこれらのツールと同じ原理で取り出すことができました。
以下は実際にオンラインやApothekeで購入可能な除去ツールの例です:
- TickCheck Premium Tick Remover Kit:ステンレス製の精密ツール付き
- O’Tom Tick Twister Zeckenhaken:回転式フックでマダニを傷めずに取り除きやすい
- Lifesystems Tick Remover Tool:シンプルな構造で携帯しやすい
- Adventure Medical Tick Nipper:ニッパー風で操作感がわかりやすい
- Kick the Tick Expert Set zur sicheren Zeckenentfernung:複数の除去具が入ったセット
- Gardigo Zeckenentferner 2er Set:基本的な2本セットでコストも抑えられる
- O’Tom Tick Twister Set 2 Stück:複数用意できるセット
- Care Plus Tick‑out Ticks‑2‑go:旅行先でも携帯しやすいタイプ
ドイツでは、WUNDmed® Zecken-Set 14-teilig のような除去+消毒用具付きセットもApothekeで購入可能です。詳細は: Shop Apothekeでチェック!
また、Tick-off® Zeckenentferner は処方箋なしで販売されている除去器具のひとつです。詳細は: Shop Apothekeでチェック!
除去のポイント
- ピンセットやフックの先端をできるだけ皮膚に近い部分にあてて、マダニの頭部をつかむように
- ゆっくり真上に引き抜く
- マダニをつぶさないよう注意
- 除去後は消毒液で傷口をきちんと清潔に保つ
消毒・抗菌・かゆみ止め薬
マダニ除去後、その部位を清潔に保ち、炎症やかゆみを抑える薬もあると安心です。
 はねうさぎ
はねうさぎ日本から持ってきていた「ムヒソフト」があって良かった!非ステロイド系で虫刺され以外の皮膚のかゆみにも効くので重宝してます。
私は血を吸われている間はかゆみは無く、少し痛みの方が強かったですが、除去した後は寝る前など一時的に痒くなることもありました。
以下は参考となる製品例:
- ムヒ(Muhi):一般的な虫刺され用の外用薬。かゆみ・炎症に効果があります。
- ムヒアルファ(Muhi Alpha EX):ステロイド+抗ヒスタミン成分を含む外用剤。腫れやかゆみがひどいときに。
- ウナコーワ:冷却感のあるローションタイプでかゆみを和らげる効果あり。
- オロナイン:抗菌作用を持つ軟膏。切り傷・すり傷などの処置に幅広く使われます。
- カルアミンローション:かゆみや発疹の緩和に使われる伝統的な成分。
ただし、これらはあくまで補助的な対応であり、感染の兆候(例:拡がる赤み、腫れ、発熱、痛み、膿など)が出た場合はすぐに医療機関を受診すべきです。
感染症リスク:FSMEとボレリア症

ドイツではマダニが媒介する感染症として、主に次の2つが知られています。
- FSME(ダニ脳炎)
脳炎ウイルスによる感染症で、南ドイツやオーストリアの一部でリスクが高い。
ワクチン(予防接種)が有効で、対象地域では無料の場合もあります。 - ボレリア症/ライム病(Lyme-Borreliose)
細菌感染で、刺し跡のまわりに「赤い輪(bull’s-eye rash)」が出るのが特徴。
抗生物質治療が必要。ワクチンはないが現在はほぼ完治する病との事。
 はねうさぎ
はねうさぎカナダ人歌手のアヴリル・ラヴィーンさんがライム病にかかったことは有名で、彼女もマダニに嚙まれていた!
いずれも、早期発見と早期治療がとても大切です。
私は、現段階では幸い感染の兆候はなく、経過は良好でしたが、今後はワクチン接種も検討しています。
マダニに刺されないための予防法

森歩きやキャンプ、ガーデニングをする人は、以下を意識すると予防効果があります。
- 長袖・長ズボン・靴下を着用(ズボンの裾は靴下に入れる)
- 明るい色の服でマダニを見つけやすくする
- 虫よけスプレー(Zeckenschutz)を活用
- 帰宅後はすぐにシャワーを浴び、体をチェック!マダニは肉眼でも見える大きさ
- 着用していた衣服はすぐに洗濯する
- ペットにもマダニ予防薬を使う(犬・猫は要注意)
- 森や草地に行くことが多い人や、庭仕事をする方はFSMEワクチンを検討
まとめ:森を歩くなら「自分は大丈夫」と思わないで

ドイツで生活していると、気軽に散歩へ行くことが良くあります。
居住地域にもよりますが、ドイツで森や草原を歩く機会は想像以上に多いもの。

今回の経験を通して、「刺される瞬間にはまったく気づかない(マダニは刺すときに痛みを感じさせない麻酔的な成分を出すらしい)」こと、「(ゆっくりと吸血するため)放置して数日後に気づく」ことが本当にあると実体験から痛感しました。
マダニは小さくても感染リスクのある生き物です。
森歩きやピクニックの後は、少しの手間でもシャワーと全身チェックを忘れずに。
 はねうさぎ
はねうさぎドイツ生活にも慣れてきて、あまりにひどい硬水と乾燥でゆっくりとお風呂に入ったり、毎日髪の毛を洗う機会が減っていたのも、気づかなかった理由のひとつかも。
そして、心配な方は、ワクチン接種を検討しておくことも、安心してドイツ生活を送るための大切な備えだと思います。


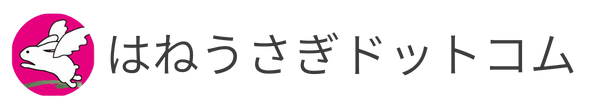









コメント